写真撮影でストロボを使い、バウンスさせて柔らかい光を作る手法はとても一般的ですが、「思ったより赤っぽく写った」「全体が黄色っぽくなった」など、ホワイトバランスのズレに悩んだことはありませんか?
私も現場でよく経験しますし、特に室内のスナップ撮影などで色味が気になるになることがあります。
今回は、そんな現場経験をもとに、
- なぜバウンス撮影でWBが狂いやすいのか
- カスタムWBとケルビン設定の違い
- RAW現像でWB調整する実践的な考え方
をまとめました。
✅直射 vs バウンス
ストロボ撮影で直射とバウンス どっちがいい?
ストロボ撮影において
**直射(ダイレクト)とバウンス(跳ね返し)**は、目的や環境によって使い分けるのがベストです。
✅ ざっくり結論から言うと:
| 条件 | おすすめ |
|---|---|
| 肌を自然に・やわらかく写したい | ✅ バウンス |
| 光が届きにくい or バウンスできない環境 | ✅ 直射(工夫して使う) |
| 場所が狭く、天井や壁が近い | ✅ バウンスが効果的 |
| 野外や天井が高すぎる場所 | ❌ バウンスは不向き → 直射 or ソフトボックス使用 |
🔦 それぞれの特徴を詳しく
📌 1. 直射(ダイレクトフラッシュ)
【メリット】
- 強くはっきりした光 → 背景までしっかり明るくなる
- バウンスできない屋外や体育館などでも使える
- クリップオンでそのまま使えるので手軽
【デメリット】
- 影が濃く・硬くなる(特に背景に影が落ちやすい)
- 肌がテカりやすく、硬い印象になる
- 被写体が白飛びしやすい
【こんな時に有効】
- スナップ・記録写真・屋外・広い会場
- ストロボ初心者がまず試すにはOK
📌 2. バウンス(天井や壁に跳ね返して使う)
【メリット】
- 光が拡散して柔らかく自然な印象
- 影が目立たず、顔の立体感がきれい
- 肌色が美しく、ポートレートに最適
【デメリット】
- バウンスする面(天井や壁)がないと使えない
- 跳ね返し距離分、光量がロスする(暗くなりがち)
- 天井や壁の色が被写体に影響する(黄色や緑の壁は注意)
【こんな時に有効】
- 室内ポートレート・証明写真・集合写真など
- 落ち着いたライティングで質感を出したい時
🎓 バウンスの基本テクニック
- 天井が白 or 明るい色 → 天井バウンス(ストロボを上に向ける)
- 右側の壁が白い → 右に向けて横バウンス(自然光風に)
- ストロボヘッドを45〜75度くらいに傾けて使う
- キャッチライトが入るように微調整(重要)
📸 おすすめ補助:
「バウンスカード(白い反射板)」は、バウンス撮影時でも目にキャッチライトを入れたり、正面からのやわらかい補助光を加えるための、非常に便利なアクセサリーです。
🔍 バウンスカードとは?
バウンスカードは、ストロボに取り付けて使用する小さな白い反射板です。
一般的には以下の2種類があります:
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 内蔵式 | ストロボ本体に内蔵(例:Canon 430EX III-RT など) |
| 外付け式 | ゴムバンドやホルダーで取り付け(大きめで効果強い) |
💡 なぜ必要? どんな効果がある?
| 効果 | 説明 |
|---|---|
| 👁️ キャッチライト | 瞳に光の反射(白い点)が入って目に生命感が出る |
| 😊 顔全体が暗くならない | 天井バウンスだけだと顔に陰が出がち → 正面補助光で改善 |
| ✨ 自然な肌トーンと立体感 | 光が多方向から入ることで、影が柔らかく自然に |
✅ 直射 vs バウンス:あなたに合った選び方
| あなたの目的 | おすすめ |
|---|---|
| 肌をきれいに撮りたい | バウンス(+補助光やフィルター) |
| 記録的に明るく写したい | 直射(+WBと露出の工夫) |
| どちらか迷う時 | RAWで撮影 → 色や露出を後から調整 |
🔶 バウンス撮影 × オートホワイトバランス(AWB)は危険?
■ 詳細な解説
1. オートホワイトバランス(AWB)とストロボの関係
- AWBは、撮影時にカメラが周囲の光源(太陽光、電球、蛍光灯など)を判断して、自動的に色温度を調整してくれます。
- ところが、外付けストロボを装着して電源を入れると、カメラは「主な光源はストロボだな」と判断し、AWBでもストロボ光(約5500~6000K)を前提にホワイトバランスを設定してしまうのです。
- このとき、自然光や室内灯などが混ざっていると、その光の色が無視され、結果的に赤っぽく(黄色っぽく)見えることがあります。
2. バウンス時や自然光混在時に赤っぽくなる理由
- バウンスすると、反射する壁や天井の色が影響して、色温度が変わります(例:木の天井 → 暖色寄り)。
- しかしカメラは「まだストロボ光が主だよね」と思って、5500K前提で処理するため、実際の色温度とズレて赤黄色っぽくなるのです。
■ 対処法・おすすめ設定
1. ホワイトバランスをマニュアル設定(Kモード)にする
- 事前に撮影環境の色温度を測って、4500K〜5000Kあたりでマニュアル設定。
- 難しければ、グレーカードを使ってプリセットを作るのもおすすめです。
2. 「雰囲気優先AWB(Canonのみ)」を避ける
- CanonのAWBには「ホワイト優先」と「雰囲気優先」のモードがあります。
- 「雰囲気優先」では暖色を残すため、さらに赤っぽくなることがあります。
- ストロボ使用時は「ホワイト優先」のほうが自然に見えることが多いです。
3. RAWで撮影して後で補正
- 混合光になる環境ではRAWで撮るのが最も確実です。
- 現像ソフト(DPP、Lightroomなど)で色温度を手動調整できます。
■ Canon・Nikon・Sonyの挙動は?
- CanonやNikonやSonyも「ストロボ使用時にホワイトバランスが固定されてしまい、赤黄色くなる」
- ストロボ装着時はAWBが「ストロボ光前提」になります。
- ただし、メーカーによってAWBのチューニングが異なり、SonyのAWBは自然光の混ざりを少し考慮する傾向があり、ややマイルドです(状況により変化)。
- Nikonも似た傾向がありますが、カメラの世代や設定項目(「色合いの保持」など)によって変化します。
🔶 カラーフィルターとは?
Canonの純正スピードライト(例:EL-1,600EX II-RTや430EX III-RTなど)には、以下のようなオレンジ色(アンバー)やグリーンのカラーフィルターが付属していることがあります:
- オレンジ系(CTO=Color Temperature Orange):電球光に合わせる
- グリーン系(Plusgreenやグリーンジェル):蛍光灯に合わせる
🔶 目的:ストロボ光を「周囲の光と揃える」ため
ストロボの光は約5500Kの「昼光色」です。
ところが、屋内では以下のような色温度の違う光源が混在します:
| 環境 | 光源の色温度 | 肉眼での見え方 |
|---|---|---|
| 室内の電球 | 約2800K(暖色) | オレンジっぽい |
| 蛍光灯 | 約4000K(緑寄り) | 緑っぽいことも |
| ストロボ光 | 約5500K(白色) | 青白く感じることも |
そのため、ストロボ光だけが不自然に浮いてしまうことがあります。
🔶 ストロボアクセサリーの使い方(実践編)
ストロボアクセサリー一覧の解説(CANON)
| アクセサリー名 | 内容・用途 | 特徴 |
|---|---|---|
| バウンスアダプターSBA-EL | ストロボ光を柔らかく広げる | バウンスしづらい環境でも自然な光に |
| カラーフィルター SCF-ELOR1 | オレンジ系(フルCTO) | 約5500K → 約3200K 電球照明(白熱灯)に対応 |
| カラーフィルター SCF-ELOR2 | オレンジ系(1/2 CTO) | 約5500K → 約3800〜4000K 暖色LEDや曇天光に対応 |
🔶 各アクセサリーの使い方と場面
◆ バウンスアダプターSBA-EL
- 装着すると、ストロボ光が広がって柔らかくなる(影が柔らかく、近距離ポートレートに有効)
- 小型ソフトボックスのような効果
- 室内の白天井バウンスが難しいときにも有効
- バウンス+アダプター併用もOK(やや減光する)
📌 使う場面:
- 天井が高すぎる/色付きの壁でバウンスが難しいとき
- ストロボ直射が強すぎると感じたとき
🔍 SCF-ELとは?
SCF-EL は、Canonのスピードライト用(特に「Speedlite EL-1」など)に用意された純正のカラーフィルターセットです。
📦 セット内容
一般的に2枚のカラーフィルターが付属しています:
| 型番 | 種類 | 色温度変換の程度 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| SCF-ELOR1 | フルCTO(オレンジ1) | 約5500K → 約3200K | 電球照明(白熱灯)に対応 |
| SCF-ELOR2 | 1/2 CTO(オレンジ2) | 約5500K → 約3800〜4000K | 暖色LEDや曇天光に対応 |
🎯 目的:ストロボ光を環境光と合わせて、色の違和感をなくす
Canonのストロボ光はデフォルトで「昼光色(約5500K)」です。
しかし、屋内の照明は暖色(電球:2800K、LED:3000〜4000K)であることが多いため、ストロボ光だけが青白く浮いて不自然になります。
カラーフィルターはそれを防ぐために:
- ストロボ光を意図的に暖色に変えて
- カメラのホワイトバランスを環境光に合わせる
ことで、写真全体が自然な色合いになります。
🛠️ 使い方
【装着】
- ストロボ前面にフィルターをはめ込む(Speedlite EL-1用に設計)
- マグネット or スライド式で簡単装着(モデルによる)
【WB設定】
- フィルターを使った場合:
- カメラ側のWBを電球(約3000K)やマニュアル設定(2800〜4000K)にする
- 上位機種(EOS R5/R6など)ではフィルターを自動検出してWB調整してくれることもあります
- RAWで撮れば後から補正も自由
📸 実践シナリオ例
| シーン | 使用フィルター | WB設定 |
|---|---|---|
| 室内(電球照明) | SCF-ELOR1(濃いオレンジ) | 電球モード(約2800K) |
| 結婚式会場(暖色LED) | SCF-ELOR2(薄いオレンジ) | 手動で3500〜4000K |
| バウンズ撮影+木天井 | SCF-ELOR2 | RAWで後補正がおすすめ |
✅ 補足:RAW現像時の利点
- カラーフィルターを使うと、RAW現像時にWB調整がしやすくなる
- 「ストロボ光=環境光と近い」ので、全体の色かぶりを抑えられる
- 複数の写真を一括補正しやすい
🔶 ケルビン固定とカスタムWB、どちらが正確?
▶ ケルビン固定(マニュアルWB):
- たとえば「5200K固定」など、自分で色温度を数値設定する方法。
- ストロボの発光色温度は約5200K〜5500Kのため、それに合わせて設定すれば一定の結果が得られます。
▶ カスタムWB:
- 実際の光をグレーカードで測定し、その画像を使ってWBを設定する方法。
- 「被写体に届いている光(=バウンス後の光)」の色温度に合わせるので、正確性は最も高いです。
🔶 ただし現実には、「撮影に集中できない」という問題が…
カスタムWBが最も正確と分かっていても、
- 撮影のテンポが大事(特に子どもや集合写真)
- 毎カットWBを測っている余裕がない
- 表情や構図に集中したい
という現場では、WBの設定に気を取られるのは大きな負担になります。
✅ 実践的な解決策:「RAWで撮って、WBはあとで直す」
これは非常に現実的で、プロの現場でもよく取られる方法です。
メリット:
- 撮影に集中できる(WBに悩まなくてOK)
- 後からLightroomなどでWBや色かぶり補正が簡単にできる
- 失敗をリカバーできる安心感がある
✅ RAW現像をラクにする3つのコツ
1. 撮影時にざっくりケルビン固定(例:4500K)
- バウンス先の天井がやや黄ばみがちな現場では、4500Kくらいが自然な肌色になることが多いです。
- ざっくり合わせておけば、プレビューの色味が近くなり判断しやすいです。
- ただし、室内の野外の撮影を行き来する場合は設定変更を忘れてしますのでオートがおすすめ。
2. LightroomでWBを一括補正
- 1枚だけWB調整 → 他のカットに「同期」すれば、大量処理が一瞬で終わります。
3. グレーカードを1枚だけ撮っておく
- 撮影の前後でグレーカードを撮っておくだけで、基準点として使えます。
- 本番中に無理せず、後処理で正確な色味に調整可能です。
✅ まとめ
- バウンス撮影では反射光の色温度にWBを合わせる必要がある
- カスタムWBが最も正確だが、現場では撮影に集中できる環境が最優先
- 結局、RAWで撮ってあとでWB調整する方が楽で失敗が少ない
現場ごとの最適解は違いますが、私の経験では「WBに悩むよりRAWで安心して撮影する」方が、結果的にクオリティも高く、スピードも落ちないと感じています。
📌 おすすめ機材やテクニック紹介
- グレーカード:X-RiteやDatacolorの信頼性高めのものがおすすめ
- ケルビン調整の目安:
- 昼光ストロボ直射 → 5200〜5500K
- 黄ばんだ天井バウンス → 4300〜4700K
- 白壁でのバウンス → 4800〜5000K
- LightroomでのWB補正:スポイトツール+「色温度」と「色かぶり補正」のバランスを見ながら調整
「色を完璧にする」ことも大切ですが、それ以上に大切なのは「表情を逃さない」「テンポよく撮る」こと。
そのためにRAW現像でWBを後から調整する、というスタイルは今の撮影現場に合った非常に合理的な方法だと、私は実感しています。
💡 プロの豆知識:
どんなに高性能なカメラでも、「届く光の色」が悪ければどう頑張っても補正に限界があるんです。
だから「どこから光が来るか」を常に意識するのがプロの照明術。
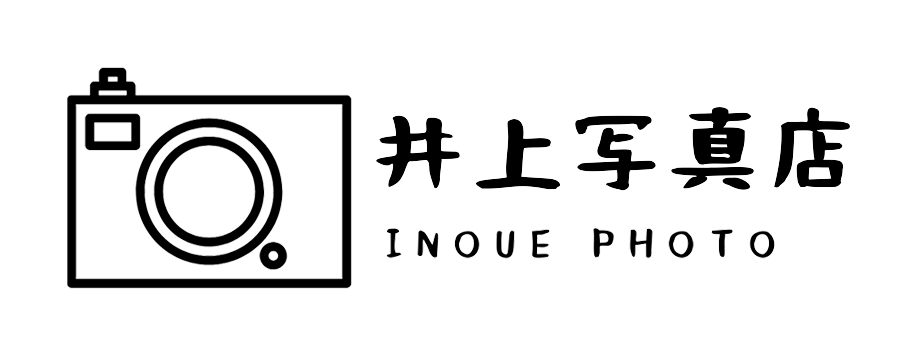

コメント